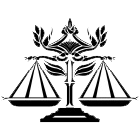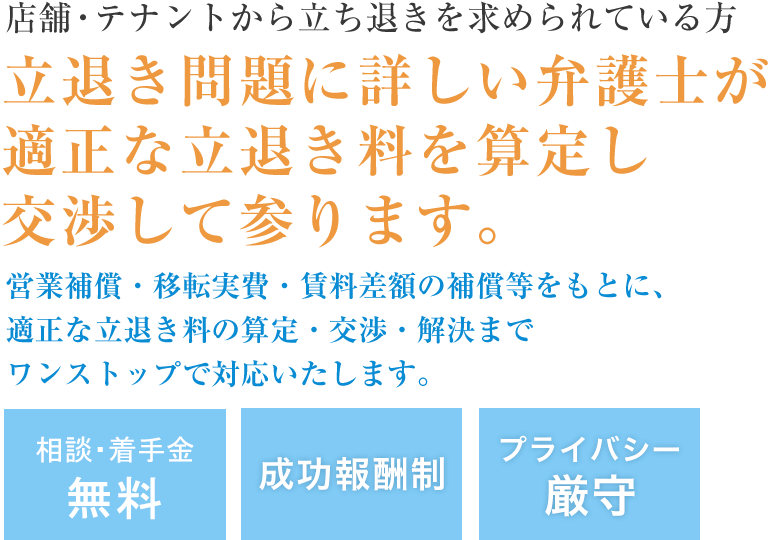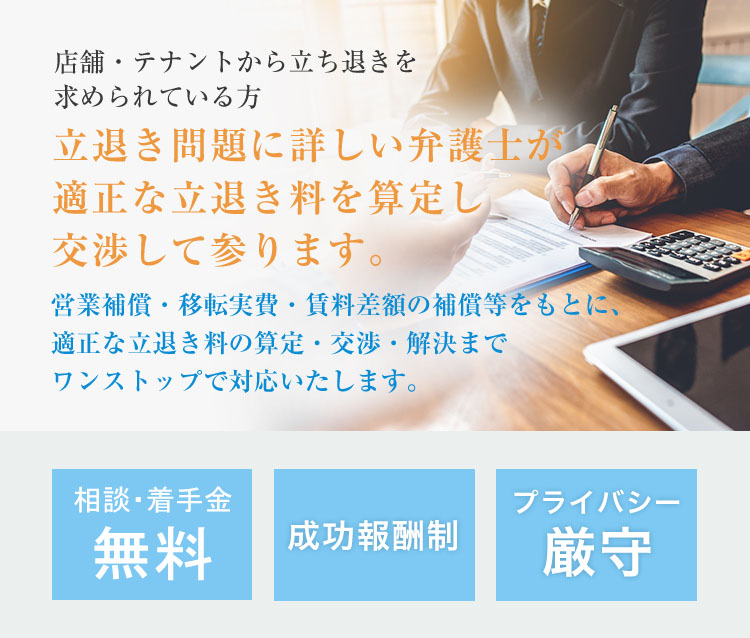立退き問題の法律相談をご検討の方、
まずはお電話・メールフォームからお問い合わせください。
- 東京
- 03-3265-498103-3265-4981
- 大宮
- 048-780-2701048-780-2701
店舗・テナントの立退きで
お悩みの方へ
よくあるご相談内容
- 建物の老朽化を理由に立退きを求められているが、
提示された立退き料の金額が不十分であり納得できない。 - 飲食店や塾など、事業内容に応じた適正な立退き料を算出したうえで、
適正な範囲で、最大の立退き料で解決したい。 - 移転に伴う営業補償、移転費用などの補償が、
立退き料で十分に補償されるなら、立ち退きに応じてもよいと考えている。 - 立ち退きを求められているが条件の良い移転先の物件が見つからないため、
損害が出ないように十分な補償をしてもらいたい。 - 大家が、賃貸借契約の更新拒絶や解約をして、
立ち退きを求めてきているが、そもそも応じる必要があるのか分からない。 - 再開発、区画整理に伴い立ち退きを求められているが、
補償金額の根拠が不明確で金額に納得できない。
立退き料の金額は担当する弁護士によって変わります
千代田中央法律事務所の強み
- 1適確な根拠をもとに、最大の立退き料で
早期解決を図って参ります。 - 営業補償、移転費用、賃料差額の補償、借家権価格等の算定要素をもとに適正な立退き料を算出し、最大の立退き料での解決を図ることで、訴訟に至る前に、両者納得のうえで早期の紛争解決を図ることが可能となります。

- 1適確な根拠をもとに、最大の立退き料で
- 2立退き問題に詳しく、
多数の解決実績を有する弁護士が
直接対応いたします。 - 店舗・テナントの立退き問題においては、営業補償の算定が主な争点になってきますが、営業補償の算定には、専門的な知見が必要となります。また、交渉によって妥結点を見つけていくため、経験に基づいた事案の見通しや妥結点を見越して交渉していく必要がございます。
この点、立退き問題を専門的に取り扱い、複数の解決実績を有している弁護士が直接対応いたしますので、迅速に最適な解決を図ることが可能になります。
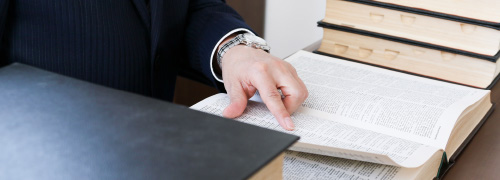
- 2立退き問題に詳しく、
- 3あらゆる立退き問題に対応することができ、
ワンストップですべての問題を解決。 - 飲食店、塾、小売店など、ご依頼者の事業内容に応じた適正な営業補償、移転費用等を算出したうえで、立退き料の最大化を図って参ります。また、合意書の作成、訴訟になった場合の訴訟対応など、立退き問題に関するすべての問題をワンストップで解決いたします。

- 3あらゆる立退き問題に対応することができ、
- 4立退き料の交渉に時間を割かずに
本業に集中できる。 - 立退き料の算定や交渉には、多大な時間と労力がかかってしまいます。この点を立退き問題に詳しい弁護士に任せることで、本業に集中でき、仮に移転する場合でも売り上げの減少を最小限にとどめることが可能となります。

- 4立退き料の交渉に時間を割かずに
- 5他の事務所で断られた案件の
解決実績も多い。 - 他の法律事務所で断られた方の案件を数多く担当し、実際に数多くの案件を解決して参りました。一見すると、賃貸人側の主張に理由があるように見える案件でも、事業内容に応じた営業補償や移転費用を緻密に算出し、法律構成を練ることで解決に導いていくことができます。

- 5他の事務所で断られた案件の
- 6訴訟による解決の場合、ご依頼者にとって
有利な解決を図ることができる。 - 立退き訴訟においては、立退き料の算定を緻密に行わなければ、不利な判決や和解内容になってしまうリスクがございます。その点、立退き問題の専門チームが、営業損失の計算など立退き料の算定を緻密かつ適確に行っていくことで、ご依頼者にとって有利な解決を図ることが可能となります。

- 6訴訟による解決の場合、ご依頼者にとって
- 7再開発・区画整理に伴う立退き要求に対して、
適正な補償金額を算定し交渉。 - 公共用地の取得に伴う損失補償基準に則って、営業廃止なのか営業休止に該当するのかを判断のうえ、営業補償、工作物補償、移転費、借地権補償料を算出し、適正な範囲で、最大の補償を求めていきます。

- 7再開発・区画整理に伴う立退き要求に対して、
About
立退き料とは
立退き料とは、賃貸人が賃借人に対し、物件からの立ち退きを求めるに当たって、賃借人の損失・不利益等を補填するために支払われる金銭をいいます。
期間満了の際に更新拒絶して立ち退きを求める場合や、解約申入れをして立ち退きを求める場合には、立ち退きを求める正当な事由が存在する必要があります。その「正当事由」の判断に際して、賃貸人・賃借人が当該物件を利用する必要性の程度、建物の老朽化の程度等のほか、立退き料の支払いが考慮されることになります。
Calculation
立退き料の
算定要素・相場について
立退き料は、賃借人の不利益を金銭に見積もって補償するものなので、事案ごとに金額は様々であり相場というものは存在しませんが、以下の三つの要素を考慮し算定されます。

営業休止・移転に伴う営業補償
立ち退きに伴い、営業を一時休業、または、移転する場合に一時休業や移転によって受ける損失に対する補償を指します。営業補償については、以下の要素を考慮して算出していきます。
- 休業期間中の収益減の補償
- 営業休止期間中も通常通り営業を行っていたら得られたであろう収益に対する補償。
- 移転により得意先や固定客を失うことに対する補償
- 店舗を移転することにより固定客を失い、売上げが減少することが予測されることから、その想定される収益減少分の損失補償。
- 固定的経費に対する補償
- 営業休止期間中でも通常通り営業を行っていた時と同様に、継続して支出される営業上の経費の補償(光熱費や電話の基本料など)、従業員に対する休業手当相当額の補償など。

移転に伴い発生する諸費用の補償
引越しにかかる費用、移転先取得のための仲介手数料、引越し挨拶状の費用、ホームページ修正費用など、移転に伴い発生する諸費用の額を算出し補償を求めていきます。

賃料差額の補償
従前の賃料が、周辺の標準賃料に比べて割安の場合など、移転することで賃料が増額する場合には、従前の賃料と、移転先の賃料の差額分の補償を求めていきます。他の補償項目との調整もありますが、賃料差額分の数か月~数年分を求めていきます。
Compensation
公共用地の取得に伴う
損失補償について
~再開発・区画整理など~
再開発・区画整理などによる公共用地の取得に伴い立ち退きを求められる場合、国や地方公共団体等の損失補償基準に基づき補償金額(立退き料)が算定されます。
国や地方公共団体等により損失補償基準は定められていますが、算出の基礎となる収益や経費の金額の算定、算定式自体に幅があることから、補償金額は確定しているわけではなく幅をもったものとなります。
Procedure
立退きを求める手続的要件
賃貸人が賃借人に対し、立ち退きを求めるに際し、法律上、以下の手続きを踏む必要があります。もっとも、手続き違反があったとしても、十分な立退き料の支払を条件に、立退きの合意をすることは可能です。
期間満了に伴う更新拒絶の場合
- 期間満了の1年前から6カ月前までの間に更新をしない旨の意思表示
- 期間満了後遅滞なく異議を述べること
解約申入れの場合
- 解約を申し入れてから6カ月経過すること
- 期間満了後遅滞なく異議を述べること
Process
解決までの流れ
- 1
- 賃貸人による立ち退きの要請
- 賃貸人からの立ち退きの要請は、書面または口頭で、老朽化や耐震性の問題といった理由でなされることが多いです。
-

- 2
- 賃借人による回答
- 賃借人としては、①立退き料の金額にかかわらず立ち退きを拒む、②立退き料の交渉をする、③提示された立退き料を前提に立ち退きに合意するといった選択をすることになります。
-

- 3
- 立退き料、その他条件の交渉
- 十分な立退き料による補償がなされるのであれば、立ち退きに応じても良いと考えている場合は、立退き料の交渉を進めていきます。その他、物件からの退去時期、建物に残置物が残っていた場合の処理方法などを調整していきます。
-

- 4
- 立退きの合意
- 交渉の結果、立退き料、その他条件の折り合いがつきましたら、立退き料の支払方法、立退きの期限、残置物の取扱い方法、その他条件を記載した合意書を作成いたします。
-

- 5
- 立ち退きの実行
- 合意内容に従って立ち退きを完了させた後、現況確認、立退き料の振込確認、鍵の受け渡し等を行い立ち退きは完了いたします。
-

Litigation
賃貸人による建物明渡請求訴訟
立退き料やその他の条件で折り合いがつかない場合には、賃貸人としては、諦めるか、裁判所に建物明渡請求訴訟を提起することになります。
訴訟を提起した後も、立退き料等の条件が整えば和解により解決することが可能です。その場合、裁判所によって和解調書が作成されることになります。
訴訟手続き中の話し合いでも和解が成立しなかった場合には、最終的に判決で決着することになります。この場合、「賃貸人が立退き料として○○円を支払うのと引き換えに、賃借人は建物を明け渡す(引換え給付判決)」といった判決がなされることがほとんどです。
Cost
弁護士費用
- 法律相談料
- 無料
- 着手金
- 無料
報酬金
- 経済的利益の額
- 金300万円以下の部分 17.6%
- 金300万円を超え
金3,000万円以下の部分 11% - 金3,000万円を超え
金3億円以下の部分 6.6% - 金3億円を超える部分 4.4%
- 経済的利益とは、獲得した立退き料の金額、又は、当初提示された金額からの増加額を指します。
- ご相談のみの場合は、30分5500円の相談料となります。
- 実費・事務費のご負担がございます。
Flow
ご相談・ご依頼の流れ
- 1
- お問い合わせ・ご予約
- お電話またはメールフォームからお問い合わせください。
担当者が基本的事項をお聞きし、打ち合わせの日時の調整を行います。 -


- 2
- 資料のご準備
- 弁護士から必要な資料をお伝えします。お手元にある分で結構ですので、賃貸借契約書、賃貸人からの通知書、決算書などの資料をご準備ください。
必要な資料か迷った場合は、お持ちいただければ弁護士が確認して参ります。 -


- 3
- 弁護士との打ち合わせ
- ご準備いただいた資料をご持参いただき、当事務所にて打ち合わせを行います。手続の流れや見通し、弁護士費用についてご説明いたします。
手続きの方針、弁護士費用等について十分ご理解いただいたうえで、弁護士との委任契約書・委任状を作成いたします。 -


FAQ
よくある質問
- Q弁護士に依頼するメリットとして、どのような点が挙げられますか。
- 最も大きなメリットとしては、営業補償や、移転実費、賃料差額の補償等から、適正な立退き料を算定することで、十分な立退き料を受け取ることができる点にあります。 大家としては、できる限り立退き料の負担を少なくして明け渡しを完了させたいと考え、少なめの立退き料を提示してきますが、立退き問題に詳しい弁護士が対応することで、適正な立退き料を獲得することが可能となります。 その他、大家との交渉の煩わしさから解放され本業に専念できる点、立退きの条件が整った際に、弁護士が合意書を作成するため、事後の紛争を予防することができます。
- Q立退き問題に関して、どの点に着目して法律事務所を選ぶことをお勧めしますか。
- 何よりも、立退き問題に詳しく、かつ、複数の解決実績を有している法律事務所に依頼することをお勧めします。 立退き問題のなかでも、店舗で事業を行っている場合には、営業補償の算定が主な争点になってきますが、営業補償の算定に詳しい弁護士は少ないのが実情ですので、営業補償の算定に詳しい弁護士に依頼することは必須となります。 また、立退き問題は、交渉によって妥結点を見つけていくという性質があるため、経験に基づいた事案の見通しや妥結点を見越して交渉していく必要がございます。そのためには、今まで複数の案件の解決実績があることも重要となります。
- Q必要な資料はどのようなものがございますか。
- まずは賃貸借契約書が必要となります。その他、大家からの立退きの要請に関する書面、店舗で事業を行っている場合には、直近の決算書2~3期分、当初の内装費が分かる請求書等がございましたら、ご持参いただければと思います。
- Q借地権のうえに家を建て居住していますが、地主から明け渡しを求められています。借地権の立退き問題を、相談・依頼することは可能でしょうか。
- 借地権に関する立退き問題のご相談・ご依頼も可能です。 借地権の立退きに関しましても、地主がいつでも自由に立ち退きを求めることは、借地借家法によって制限されています。 地主が明け渡しを求めるためには、当該土地を利用する必要性や、今までの経緯のほか、立退き料の支払いを考慮する必要があります。一般的には、立退き料によって、借地人の不利益がどれだけ補償されるかが重要となりますので、立退き料の金額の妥当性が争点となってきます。
- Q契約書をみると定期賃貸借契約となっていますが、この場合でも立退き料を求めることはできますか。
- 定期賃貸借契約の場合には、立退き料を請求することはできません。 定期賃貸借契約は、一定の期間をもって賃貸借契約が終了すること、その際に借地借家法の立退き料に関する規定の適用がない契約となりますので、期間満了に伴い立ち退きを求められている場合には、立退き料を請求することはできないことになります。
- Q居住用としてマンションの一室を借りていますが、立退きを求められています。立退きの相談・依頼をすることは可能でしょうか。
- 居住用物件の立ち退きに関しても、対応可能です。 もっとも、想定される立退き料の金額が少額で、実費や弁護士費用を考慮するとご依頼人にメリットがなく、無理に弁護士が介入すべきではない事案に関しては、その旨お伝えさせていただきます。
立退き問題の法律相談をご検討の方、
まずはお電話・メールフォームからお問い合わせください。
- 東京
- 03-3265-498103-3265-4981
- 大宮
- 048-780-2701048-780-2701
Introduction
事務所紹介
様々な店舗・事業者の立退き問題に精通した弁護士が直接対応いたします。
当事務所では、取扱業務分野を絞り、同分野に特化していくことで、多くの案件を集中して解決していくため、裁判所の傾向の把握や、交渉スキルを含めたノウハウの蓄積が充実しており、実態に即した柔軟な解決を迅速に行うことが可能となっております。

東京オフィス
〒102-0085
東京都千代田区六番町六番地一 パレロワイヤル六番町704号
- アクセス
- JR四ツ谷駅(麹町口)、丸ノ内線・南北線四ツ谷駅から徒歩4分
JR市ヶ谷駅、都営新宿線・南北線・有楽町線市ヶ谷駅から徒歩5分
有楽町線麹町駅から徒歩7分
大宮オフィス
〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目89-1 タカラビル4階
- アクセス
- JR大宮駅(東口)から徒歩7分
Lawyer
弁護士紹介
- 佐藤 聖喜
- 京都大学経済学部卒業
最高裁判所司法研修所
日本弁護士連合会・東京弁護士会
- 前垣 涼太
- 東京大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所
日本弁護士連合会・東京弁護士会
- 寅本 章人
- 慶應義塾大学法学部卒業
東京大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所
日本弁護士連合会・東京弁護士会
- 藤本 彰則
- 大阪大学法学部卒業
大阪大学大学院高等司法研究科修了
最高裁判所司法研修所
日本弁護士連合会・東京弁護士会
- 金子 龍太郎
- 早稲田大学法学部卒業
東京大学法学政治学研究科修了
最高裁判所司法研修所
日本弁護士連合会・東京弁護士会
- 岩崎 静寿
- 中央大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所
日本弁護士連合会・東京弁護士会
- 佐藤 圭太
- 学習院大学法学部卒業
学習院大学法科大学院修了
最高裁判所司法研修所
日本弁護士連合会・埼玉弁護士会
- 松岡 佐甫子
- 中央大学法学部卒業
中央大学大学院法務研究科修了
徳島地方裁判所 裁判所書記官
最高裁判所司法研修所
日本弁護士連合会・東京弁護士会
- 牛木 優
- 中央大学法学部卒業
東京大学法学政治学研究科修了
最高裁判所司法研修所
日本弁護士連合会・東京弁護士会
- 春木 佳佑
- 京都大学法学部卒業
京都大学大学院法学研究科修了
司法試験予備試験合格
最高裁判所司法研修所
日本弁護士連合会・東京弁護士会
- 野々村 穂高
- 中央大学法学部卒業
首都大学東京法科大学院修了
最高裁判所司法研修所
日本弁護士連合会・東京弁護士会
- 小宮 義隆
- 東京大学法学部卒業
東京大学法学政治学研究科修了
最高裁判所司法研修所
日本弁護士連合会・埼玉弁護士会
Contact
お問い合わせ
まずは無料でご相談ください